
こんにちは。
デイサービス長老大学 代表の澤本洋介(@sawamoto482)です。
2016年9月4日に大阪中之島公会堂で開催された「大阪戦場体験証言集会・シンポジウム」の第2部に長老大学職員の太田翌花さんが登壇してきました。
(太田さんが登壇することになった経緯はコチラの記事をどうぞ→戦場体験証言集会・シンポジウム(9/4大阪・中之島公会堂)に長老大学介護スタッフが登壇します。 - デイサービス長老大学のブログ)
私も裏方として参加させていただきましたが、大変素晴らしいシンポジウムでした。
「高齢者とともに未来を創る」をモットーとして活動しているデイサービス長老大学にとって、得るものが多く、今後の活動方針を考える良いきっかけともなりました。
以下、レポートです。
第一部「語らずに死ねるか」
第一部は「語らずに死ねるか」というタイトルで、15名の戦争体験のある皆さま(平均年齢90歳以上)がご自身の貴重な体験をスピーチしてくださいました。
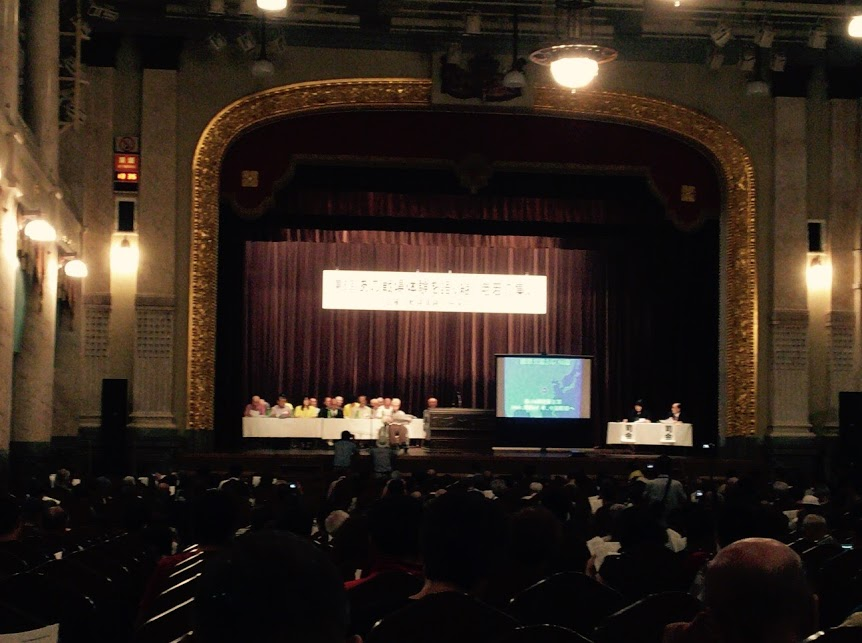
沖縄、中国、フィリピンでの凄惨な戦闘のお話や、日本国内での空襲のお話、シベリア抑留のお話、加害者としてのお話など、それぞれの皆さまの「語らずに死ねるか」というお話はとても強烈でした。
ほとんどの登壇者の皆さまが、「二度と戦争をおこしてはいけない」と話していたこと。
また、このイベント自体は政治的に「無色」でしたが、登壇者の皆様の個人的なご意見としては、権力に対して批判的な方が多かったことも印象的でした。
いつの世でも為政者の責任転嫁は歴史の事実です。表の政策には眉につばをつけ裏面を探ってだまされないように勉強しましょう。
それも、その方の、心からの「語らずに死ねるか」というお気持ちなのだろうと思います。
後述しますが、第二部に登壇されたノンフィクションライター城戸久枝さんが出演されたMBSラジオ「報道するラジオ(2016年9月5日放送分)」に、第一部に登壇された2名の方のスピーチの様子が公開されています(11分25秒頃~、16分30秒頃~)。ぜひ実際の声をお聞きください。
9月5日(月)放送分「戦争を聞く」ノンフィクションライター 城戸久枝さん
介護職という仕事柄、90歳前後の皆さまが15名お集まりになる場合について、あれこれと必要な介助体制について考えていましたが、皆さま本当にかくしゃくとされ、控室で太田さんと共に驚いていました。
戦後、様々な社会活動に参加されたいた方が多いようで、介護予防と「活動・参加」について考える上で大きなヒントを頂いたような気がします。
関東圏から中之島集会に参加、昨晩遅く帰京したの体験者の方(91歳)の携帯に、「お疲れが出てませんか」と電話をしたら一瞬口ごもられた。あっ、やっぱり強行軍だもの!と思ったら、「今グラウンドゴルフをしてるんだよ」。お疲れモードは私だけなのか・・・。
— 戦場体験放映保存の会 (@JvvapJP) 2016年9月5日
後からどっと疲れが出るのでは?と心配していましたが、主催者の方のTweetからお元気な様子が伝わり嬉しくなりました。
第二部「あなたにもできる!身近な体験談の聞き歩き」
第二部は、家庭・学校・介護施設という3つの現場から、「戦争体験を語り継ぐ」活動に関わっている3名の方が登壇されました。
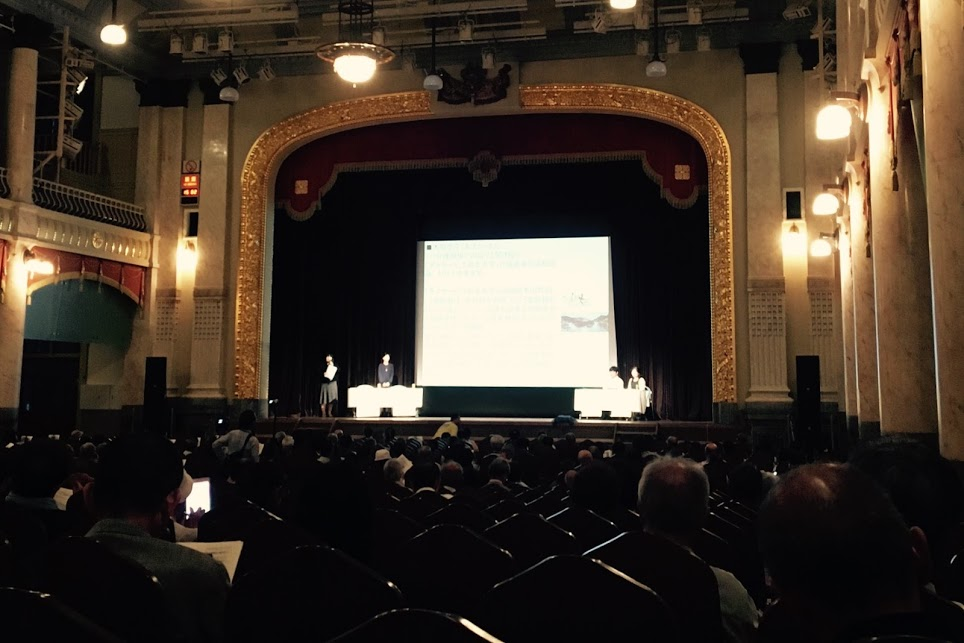
一人目の登壇者はノンフィクションライターの城戸久枝さん。
ご家庭で、中国残留孤児であったお父様から聞き取り活動をされ、『あの戦争から遠く離れて―私につながる歴史をたどる旅 (文春文庫)』という本を出版しておられます。
城戸さんからは、家族だから聞けることや家族だからこその難しさなどをお話していただきました。

あの戦争から遠く離れて―私につながる歴史をたどる旅 (文春文庫)
- 作者: 城戸久枝
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2012/09/04
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 4回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
この本は、NHKに遥かなる絆 というタイトルでドラマ化されていますので、ご存知の方も多いだろうと思います。
前述のラジオ放送もぜひお聞きください。
9月5日(月)放送分「戦争を聞く」ノンフィクションライター 城戸久枝さん
語り部の方が主人公になって、聞き手はあくまでも聞き手という立場になっている形から、これから変わっていくべきじゃないかなと思っていて。
聞き手が今度は主人公となって、そしてどういうふうにそれを語り継いで、次に受け継ぐ一つのかけ橋のような存在に、直接聞ける世代がなっていくべきじゃないかなと思っていて。
城戸さんは、聞き手である私たちが、それをどのように受け継ぎ伝えるかを次回作のテーマとして考えておられるそうです。次の本も楽しみにしています。
二人目の登壇者は、沖縄県立名護商工高校の教頭先生である功刀弘之さん。
功刀さんからは、商工高校観光コースの学生さんが、自分たち沖縄戦の体験者の皆さんに聞き取り活動を行って戦跡を歩き、それを発表するという平和学習の取組みをお話していただきました。
将来観光産業に関わる若者達にこそ、直接経験者から歴史を学び、次世代の語り部となって欲しいという思いには大変共感しましたし、城戸さんがラジオでお話された「聞き手が主人公になる」という、まさにその実践がおこなわれている現場です。
学生の皆様が聞き取り活動をしている様子が映ったニュース映像も見せていただきましたが、とても頼もしく感じました。
三人目の登壇者は、デイサービス長老大学の太田さん!
太田さんは、毎日、入浴・食事・排泄などの介護業務を行いながら、ご利用者さんのお話の聞き書きにもとても熱心に取り組んでくれています。(長老大学は他の職員さんもみんな凄いです。)
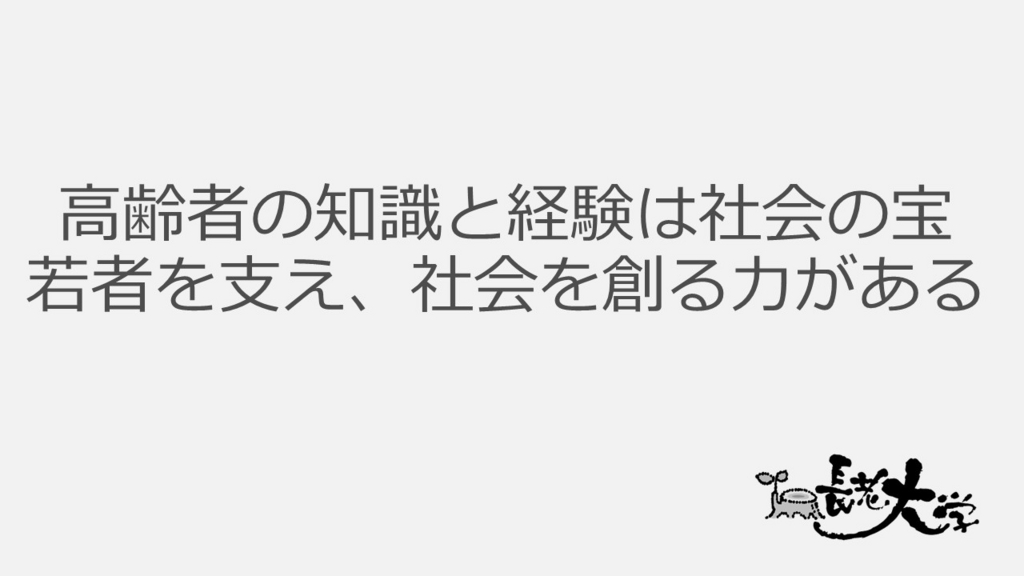
「長老大学」の名前の由来でもありますが、私たちは、 ご高齢のみなさんの知識と経験は社会の宝。
若者を支え、社会を創る力がある!と考えています。デイサービスのご利用者さんが実際に経験することで得てきた知識や知恵、 つまり、暮らしの中で失敗や成功やいろいろあった、その経験のなかには、 私たちが何かをしようとしたり、考えたりする時の支えになるようなヒント(気づき)があると思っています。
そのヒントこそが宝です。
ご利用者さんのお話を聞くことは宝探しをしているみたいだなぁと思います。
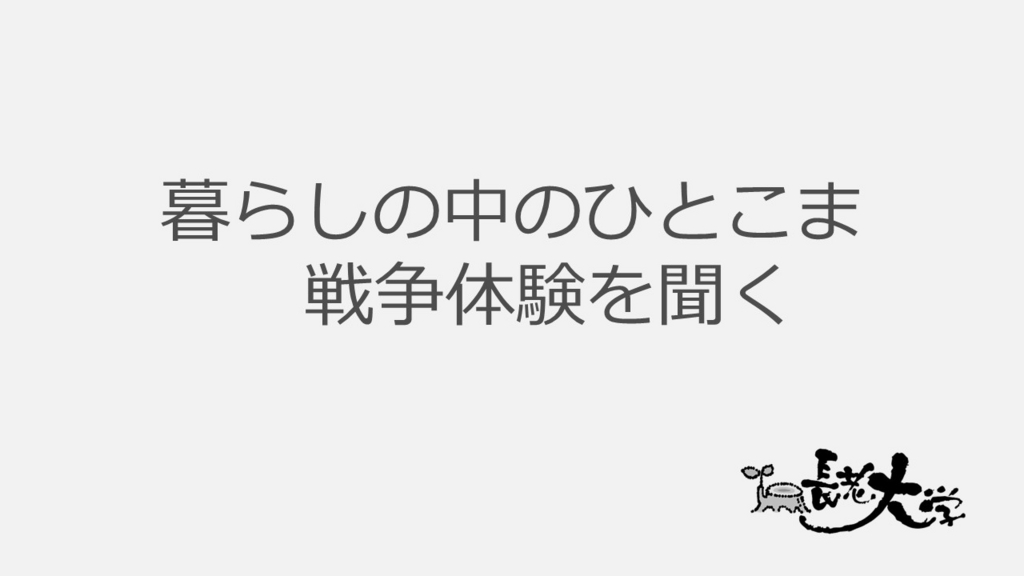
デイサービスは生活支援の場なので、
ご利用者さんには穏やかで楽しみな時間を過ごしていただきたい、と思っています
なので「聞き書き」の時に私たちの方からご利用者さんに戦争体験をお聞きすることはしていません。
それでも、色々なお話を聞いていると戦争に関わるお話になることも多いです。
70年、80年、90年と続いてきたその方の暮らしの中に
どんなふうにして「戦争の日々があった」のかという事を知ることになります。
長老大学では積極的に特別に「戦争の話」を聞くことは行っていません。
しかしそれでも、「宝探し」のように、さまざまな昔話をお聞きして、信頼関係も築けていくうちに、戦争の話をお聞かせいただくことも少なくありません。
太田さんは、長老大学の聞き書きメモより、とあるご利用者さんの国防婦人会の頃の思い出を読み上げてくれました。
見送りに行ったときは、戻るか戻らんかわからないので泣き別れ。
泣いたら怒られるのでがまんした。終戦で3か月ほどして帰ってきた。
今はどこの国でも行き来できてよい。
昔は喧嘩のし合いだったから行けなかった。国どうしが戦争はおかしい。今は幸せな時代。好きなようにできる。あんきなもんでよ。
不思議なことよ。不思議なことよ。
太田さんは、現場の実践者だからこそのお話をしてくれました。
私にはできない、とても良い発表だったと思います。
今後のデイサービス長老大学について考えたこと
私たちは、「話を聞くデイサービス」としては、全国的にも先進的に取り組んでいる方だと自負しています。
しかし、まだまだ、自ら語り部となり高齢者の皆様の貴重なお話しを次世代に繋いでいくところまでは実践できてはいません。
戦争体験や、地域の歴史などを次世代に語り継ぐことは、介護現場が生み出すことのできる大きな価値のひとつだと思います。
長老大学として具体的に取り組めることは何か?
半年に一度の開催が義務付けられている運営推進会議の議題にし、ご利用者さん達と共に考えたいと思います。
シンポジウムには、ウチの9歳と5歳の子ども達も連れていきました。
子ども達にも響くものがあったようです。
これも、次世代へ繋ぐ小さな一歩になったかもしれません。
一緒に参加できて良かったです。
以上、レポートでした。
主催者の方の運営する戦場体験史料館にも、当日の証言などが公開されるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。
